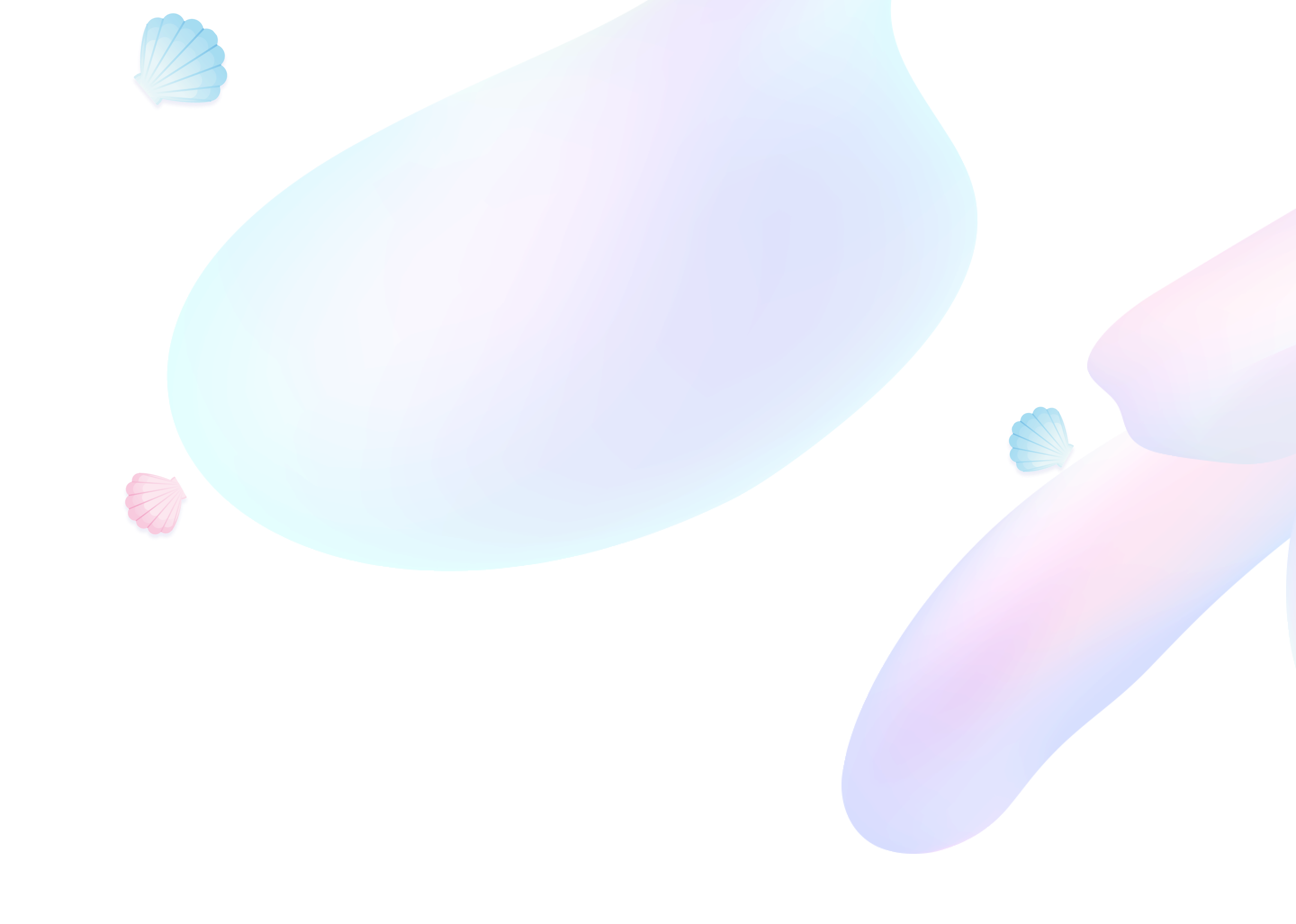
研究ノート:星加良司『障害とは何か』―ディスアビリティ理論の再検討Ⅰ #2
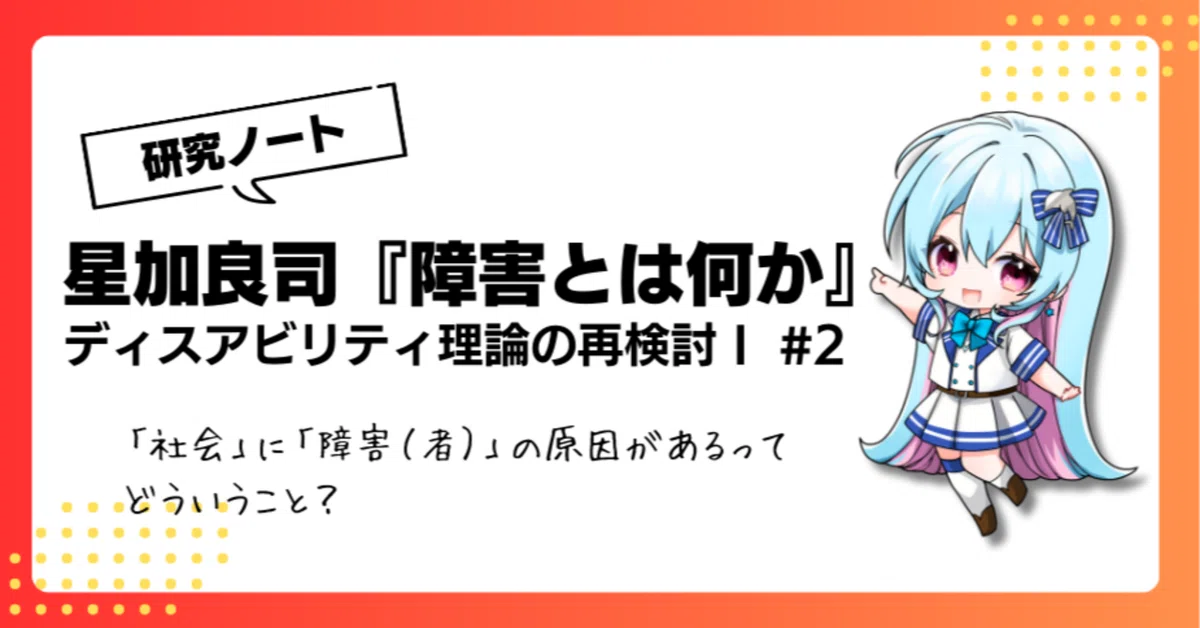
前回は、社会に原因を持つという事実によってディスアビリティが他の不利益と区別できないということを確認した。
🟩前回の記事はこちら👇️のリンクからどうぞ!
🟩テキストはこちら👇️です
障害とは何か: ディスアビリティの社会理論に向けて
目次
1.ディスアビリティの不利益の同定
1. インペアメントの関係から
そこで、ディスアビリティを他の不利益と区別するために別の基準を必要とする。それが「インペアメント」との関係で捉える見方である。
端的に言えば、「ディスアビリティとはインペアメントのある人の問題だ」ということだ。
(星加2007: 107)
(例)
UPIASの定義:「ディスアビリティとは我々を社会における完全な参加から不必要に阻害し排除するという仕方で、インペアメントの上に押しつけられた何物かである」
オリバーの定義:「(1)インペアメントがあること、(2)外的に押しつけられる制約を経験していること、(3)障害者として自己を同定していること」
2. 後続カテゴリーとしてのインペアメント
しかし、星加はこの見方を採らないという。
それは、インペアメントはディスアビリティの存在から遡及的に措定されるものであると考えるからだ。
(星加2007: 108)
元を辿れば、ディスアビリティはそれとして発生ないし創出されているのであって、インペアメントはあくまでも後続のカテゴリーだから、ディスアビリティをインペアメントとの関連で同定することには無理がある。
(星加2007: 108)
3.ディスアビリティとインペアメントの併存
しかし、星加は「社会的現実にとっては両者は併存している」(星加2007: 109)のだから、インペアメントとの関連でディスアビリティを同定する可能性も残されているかもしれないと言い、ディスアビリティ同定の論理を再解釈することは可能だろうか、と問いを立てる。
このとき、インペアメントの存在を要件とすることは可能だが、それは不利益を生む他の可能的要件を措定した場合とどう異なるのかについては何も答えていないと星加は指摘する。
たとえば、「体が人並みはずれて大きい人」や「田舎で生まれた人」にとっての不利益ではなく、「インペアメントのある人」にとっての不利益だけがなぜディスアビリティとして把握され、その解消が特に要請されるのかが不明なのだと主張する。
4. 問題の「特権化」に伴う危険性
さらに星加は、「ディスアビリティは、インペアメントが当事者にとって両義的なものでありうるのとは対照的に、端的に不利益の経験である点で否定的なものである(星加: 2002)」という自身の主張を引用し、それゆえその解消は当事者にとって望ましいものであることは疑わないが、その妥当性を示す論理が構築されていない場合、当事者にとって否定的な契機を含むと主張する。
なぜなら、「ある種の「問題」だけが、妥当性を問われることのない領域として「特権化」されるとき、そこには暗黙の否定的な価値付与が生じやすい」(星加2007: 110)からだ。
星加は続けてこう述べる。
なぜ障害について我々が特に関心を払わなければならないのかについて、十分な議論がなされておらず、それは同時に、障害を「特別」な「弱者」の問題として捉えようとする社会通念と用意に結び付くことにもなるのである。
(星加2007: 110)
🟦パーソナルノーツ1:星加の主張
1. なぜ「インペアメントのある人」の不利益だけがディスアビリティとして扱われるのか?
星加の問題意識は、「不利益を生む要件が他にもあるのに、なぜインペアメントに起因する不利益だけがディスアビリティとして認識され、解消が求められるのか?」ということである。
星加が例にしたのは、
①「体が人並み外れて大きい人」
建物の構造が体に合わない。扉が小さすぎる、席が小さすぎるなど。
②「田舎で生まれた人」
雇用機会に恵まれない。公共交通機関の不備で移動が不便など。
これらも「社会構造による不利益」だが、「ディスアビリティ」として扱われることはない。その一方で、「インペアメントのある人」の不利益だけがディスアビリティとして特別に認識されるのはなぜか。その理由が明確ではないという指摘だ。
2. ディスアビリティの「特権化」と否定的価値付与
星加が言う「特権化」とは、「ディスアビリティが特別に扱われること」すなわち「他の不利益とは異なるものとして特別視されること」であろう。
たとえば、「ディスアビリティは特別な支援を必要とする問題だ」とすれば、それは「障害者は常に支援を受けるべき存在」と見なされることにつながる。
また、「特別に支援を受けるべき存在」として扱われることで、「障害者は支援を受けるのが当たり前」「障害者は社会に負担をかける存在」といった否定的な価値付与が生じやすくなる。これは、障害者にとって必ずしも望ましい状況ではない。
まとめ
星加は「ディスアビリティだけが特別視される理由を明確にしないと、障害者に対する否定的な意味付与」が生じやすいと主張している。
🟦パーソナルノーツ2:藍沢による批判・検討
1.理論と社会的現象の混同
━━━━━━
続きはnoteで公開中
この先の詳細な考察は、noteの有料記事でご覧いただけます。
🔹 続きを読む ➡ 研究ノート:星加良司『障害とは何か』―ディスアビリティ理論の再検討Ⅰ #2
ぜひチェックしてみてください!
あなたのご支援が、さらなる記事執筆の励みになります。
━━━━━━
