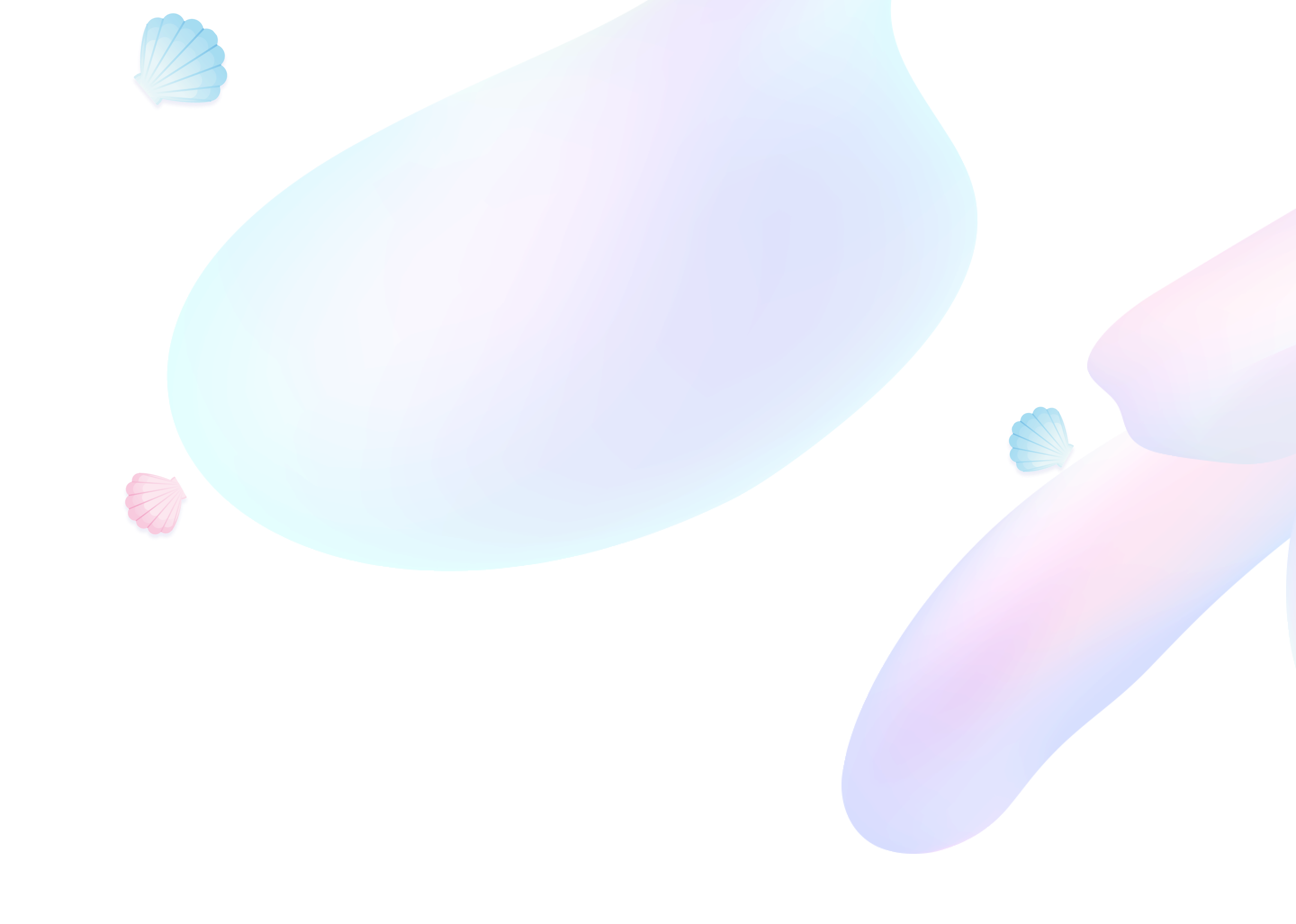
研究ノート:星加良司『障害とは何か』―ディスアビリティ理論の課題 #3
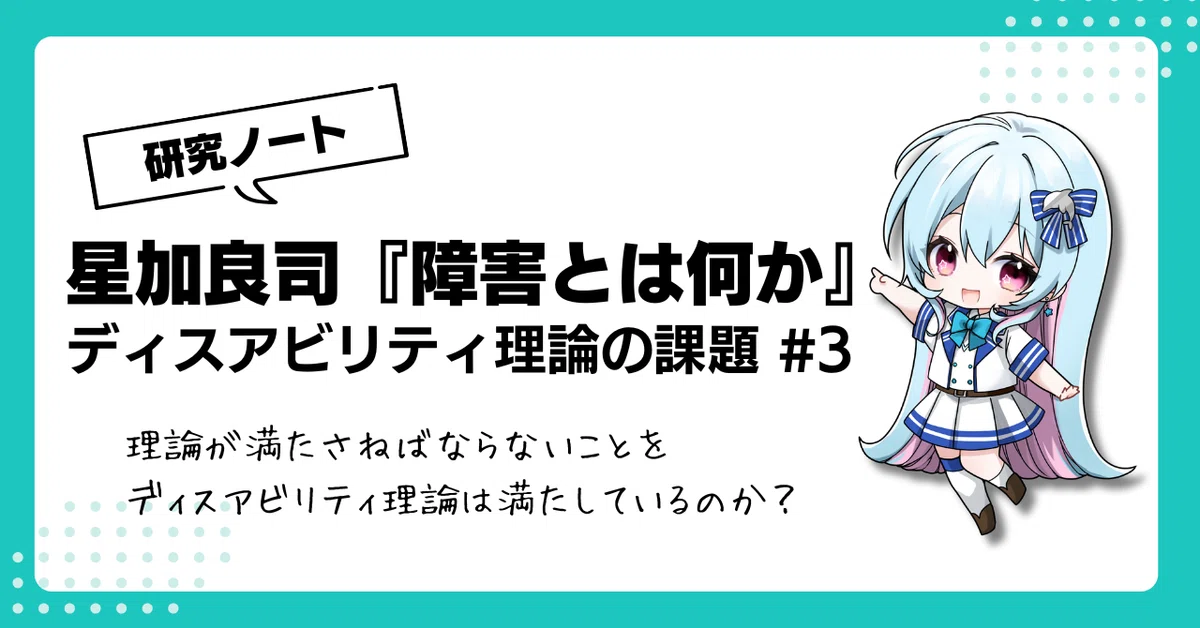
🟥前回の記事は、こちら👇️のリンクからどうぞ!
🟥テキストはこちら👇️
「自己決定」の価値化
自己決定
障害者の自立生活運動は、障害を持つ当事者の「自己決定」に基づいた生き方を目標としている。ここでは「自己決定」が「自立」概念のキーワードになっている。
これは、それまで家庭や施設において、他者の決定によって生活が管理されてきた障害者の切望である。
自己決定権と自己決定能力
しかし、「自己決定」を強調することは、「自己決定」できる人の価値を高める結果となり、新たな抑圧を生む。この点について、星加は立岩真也の議論を参照しながら説明する。
立岩は、「自己決定」に人間としての本質的な価値を見出そうとする「自己決定主義」とも呼びうる考え方の問題点を指摘する。すなわち、「ある個人の存在の尊重」は、「自己決定」や「自己決定能力」の有無に左右されるものではない。さらに、我々の生活には、「自己決定しないことの快」が存在する。自ら決定することのできない周囲の世界から受け取る快は、人間の生活にとって不可欠な要素である。
こうした観点から、星加は「自己決定」や「自己決定能力」を問うことが持つ抑圧性を指摘している。
「自己決定」とディスアビリティ理論
星加は、「自立」や「自己決定」について、ディスアビリティ理論は「多様性要求」「解消可能性要求」に応えられていないのではないかと指摘する。「自己決定能力」の高低による選別・序列化は、多様な障害のあり方を包摂しないし、ある種の人々にとってはむしろ解消不可能なものとして不利益を規定してしまっている。
このことは、記述的で二元論的な理解を前提とするディスアビリティ理論の図式が、従来の「自己決定」理解に反映していることと関連している。すなわち、社会的文脈と切り離された個人において生じている制約的な状態としてディスアビリティが理解されることで、それを解消しようとする様々な働きかけが個人を焦点にしてなされることになり、個人に内在するものとしての「自己決定能力」を浮上させることになっているということである。
星加良司,2007,『障害とは何か』生活書院: 89-90
また、ディスアビリティ理論が制度的位相にのみ照準するために、他者との関係や相互行為における不利益の生成や解消という点を軽視していると言える。
