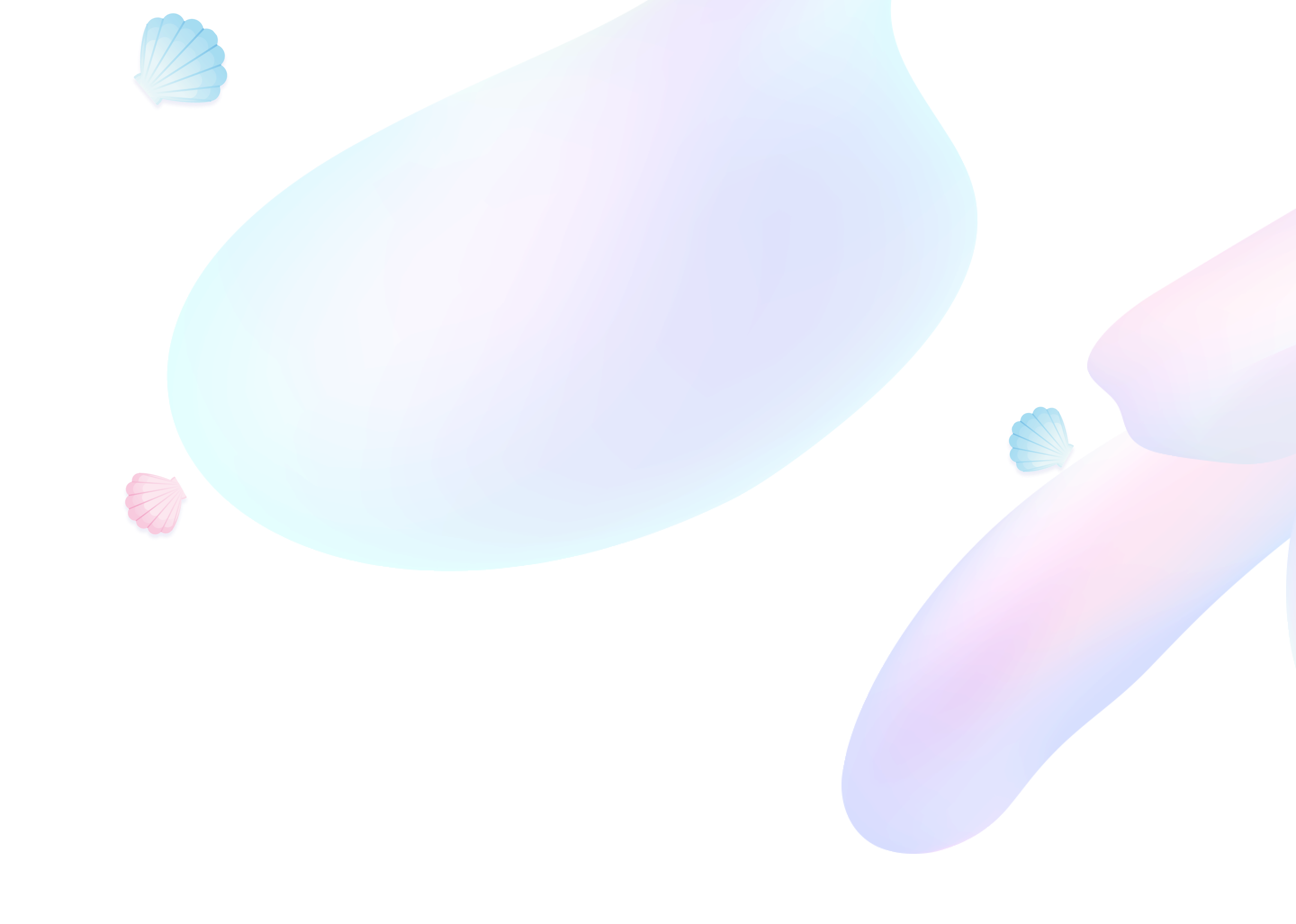
【推しの子】最終話 考察 ~社会学視点から~
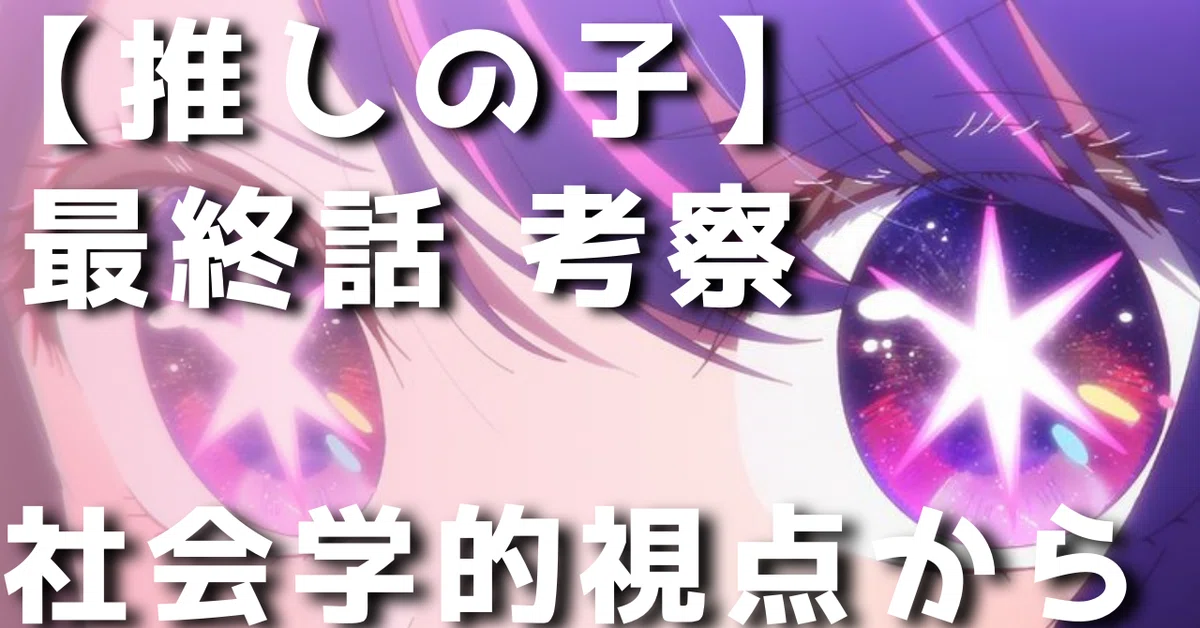
最終話のあらすじ
【推しの子】最終話では、ルビーが兄・アクアの命を丸ごと背負い、彼の遺志と母・アイの願いを胸に、未来へ進む姿が描かれました。
ルビーは、アクアを失ったことで抱えた苦しみや悲しみといった心の闇を「嘘」で隠し、無理にでも笑顔を作ってステージに立ち続けます。それでも、ここぞという時には、その闇さえも力に変えて人々に訴えかけます。
一方、世間はルビーの身に起きた悲劇を「リアリティ溢れる物語」として解釈し、彼女の物語に夢中になって目を離せなくなります。そうしてルビーは、希望のない真っ暗闇の世界を照らす光となり、母・アイのような存在へと成長していきました。そしてついに、彼女は念願だった東京ドーム公演を果たします。
物語は、星野ルビーという一番星のさらなる輝きを予感させながら、静かに幕を閉じました。
社会学者としての視点
【推しの子】で象徴的に登場する「【⠀】」は、社会学でいう「役割(期待)」、あるいは「ペルソナ」を思い起こさせます。人は皆、社会の中で複数の役割を演じており、【⠀】(ペルソナ)はその本質を端的に表現しています。
その中でも【アイドル】や【芸能人】という【⠀】(ペルソナ)は、特に虚構に彩られた役割と言えます。【推しの子】はその虚構がもたらす救いと重荷を、鮮やかに描き出した作品でした。
しかし、最終話で惜しく感じたのは、【アイドル】や【芸能人】という【⠀】(ペルソナ)が、社会的にどのように期待され、消費されていくのかについて、もう一歩深く切り込んで欲しかった点です。
昨今、SNSでの誹謗中傷が社会問題となっていますが、それは世間が対象の一面しか見ず、ひとつの【⠀】(ペルソナ)だけで判断し、評価を下してしまう構造そのものです。そうして都合よく作り上げられた「真実」を信じ込み、それ以外の可能性に目を向けなくなる。この現象は、作中でアクアが言った「世間は真実を求めない」というセリフに集約されているとも感じます。
最終話では、このような現代社会の課題に対して警鐘を鳴らす余地がありました。それが形にできていれば、物語全体のテーマと強く結びつき、より多くの読者に深い問いを投げかける結末となりえたのではないでしょうか。
「世間は真実を求めない」という問い
アクアがカミキヒカルを殺す場面で放った「世間は真実を求めない」という言葉。この言葉には、SNSをはじめとする現代社会の課題が凝縮されています。私たちは多様な視点を持つどころか、都合の良い「真実」を信じ、自らが演じる役割をもその「真実」に従わせています。
【推しの子】はその現実を提示することには成功しましたが、締めくくりでその問題をどう乗り越えるのか、SNSの使い方や他者との向き合い方について、さらに深いメッセージを示すことができたなら、この作品のテーマはより強く響いたのではないかと思います。それが可能な力を持った物語でした。
【推しの子】というフィクションへの読者としての敬意
【推しの子】が描いた物語は、「嘘」と「真実」の間にある虚構性と、その中で人々がどのように他者と向き合うべきかを問いかけているようにも見えます。ただ、最終話ではその問いが明確には提示されず、物語としての完成度を惜しく思う部分もありました。
それでも、この作品が社会に問いを投げかけ続ける力を持っていることは間違いありません。
ルビーが歩む未来と、【⠀】(ペルソナ)とともに生きる私たち、そして一面的な【⠀】(ペルソナ)が私たちに作らせる「真実」をどう捉えるべきか。それを問い続けることこそが、この物語への敬意の示し方であり、私たちに与えられた課題なのではないでしょうか。
※こちらの無料記事は現在、有料記事として加筆中です。その考察を元に、動画用台本や案の提供も可能です。興味ある方はDMでご相談ください!
